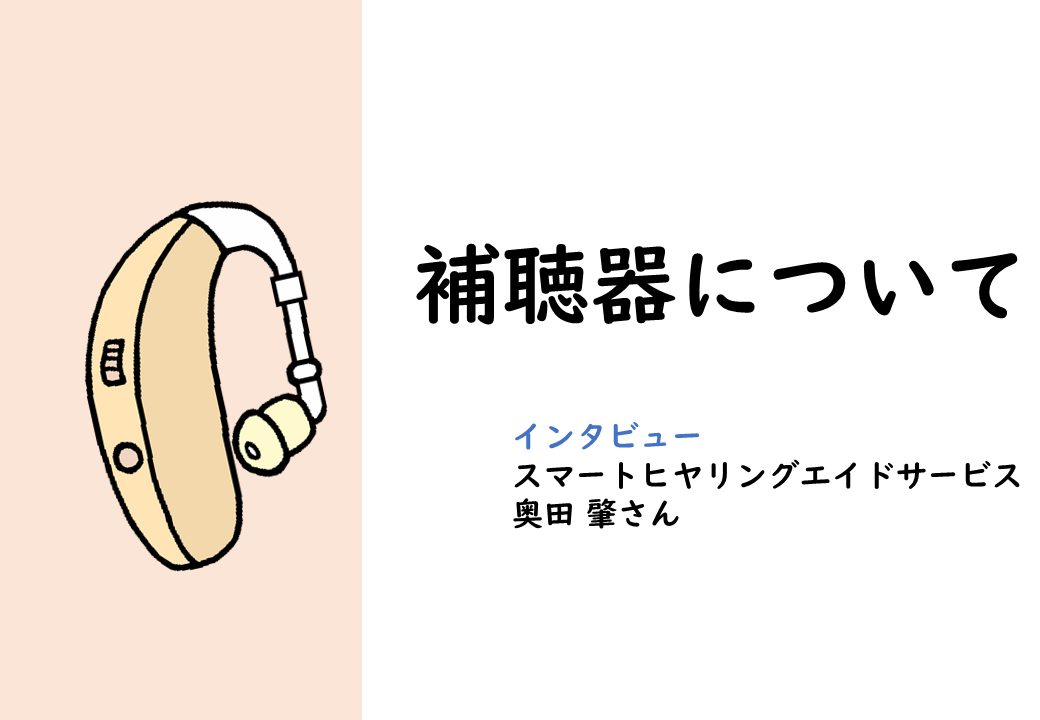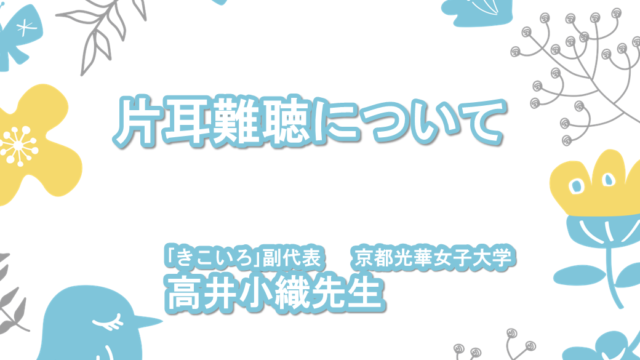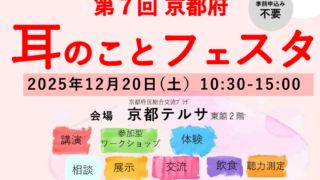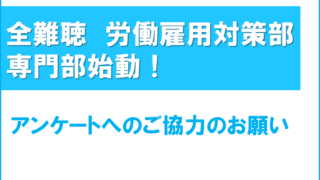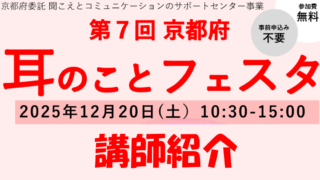補聴器の購入を検討する際に「どこで買えばいいの?」「どんな補聴器があるの?」と悩まれる方も多いと思います。今回は補聴器店スマートヒヤリングエイドサービス 副代表 奥田肇様にインタビューを行いました!ぜひ補聴器購入時の参考にしてください。
奥田 肇(おくだ はじめ)
認定補聴器技能者。
補聴器店スマートヒヤリングエイドサービス副代表。
全国チェーンの補聴器販売会社で約16年間、店長、エリアマネージャー、本社技術/商品仕入/営業責任者を歴任。約15年前に、補聴器販売店スマートヒヤリングエイドサービスを共同で設立(スタッフ4名)。現在までに関わった補聴器相談は5,000件以上。
私どもは出張サービス型補聴器店です。耳鼻科クリニック(補聴器相談医)、介護サービス事業所、地域包括支援センター、福祉用具取扱い業者等からご紹介いただいたうえで、ご自宅・入所先へお伺いしています。
様々な測定機器を持ち込んで、
問診→外耳道観察→聴力測定→機種選択・試聴→装用練習→貸出開始をしており
その日の内に約2時間で完結しています。(※ただし予約制)
聞きづらさの問題が解決したらご購入、そうでなければご返却いただきます。
来店不要なので、特に交通手段の限られた方、外出困難な方に喜ばれております。
まずは耳鼻科クリニック(補聴器相談医)を受診することが推奨されます。
そして聴力検査(測定)の結果が、40dB以上の中等度難聴、もしくは聴力レベルに関わらず、生活の中で聞きづらさを感じている場合は補聴器を検討します。
※耳鼻科診療マニュアルより抜粋
補聴器の形や色も様々あります。スタッフと相談しながら、まずは無償貸出を受けて、日常生活の中で試してみることがポイントです。
購入後のアフターサービスについても、きっちり事前確認したいですね。補聴器の寿命はおおよそ6〜7年。半年毎のメンテナンスをきっちり受けていかないと、この寿命もさらに短くなることもあります。
どの補聴器メーカーも、
・エントリー・ベーシック・スタンダード・ハイスペック・プレミアムなど、
性能・価格差によってクラス分けがされています。上位のクラスになるほど、雑音抑制や会話強調の機能が追加されていきます。
上位クラスでないと、拡張機能(ロジャー等)、紛失保証等も受けられません。
★全国の補聴器平均売価17万円/2023年(前年比+1万円)
※日本販売店協会機関誌fittingより抜粋
無償貸出を受けてもらうのが良いです。合わなかったら違う形やメーカーで再貸出を受けてください。補聴器の効果が感じられない方の中には、正しく操作が出来ていない場合もあるので注意です。
SNSだけに頼って選ぶのではなく、耳鼻科医(補聴器相談医)や、介護サービスを受けておられる方なら、ケアマネジャー等介護関係者にご紹介していただくと無難です。
あとはお店のアクセスの良さや、スタッフとの相性です。
AI(人工知能)搭載のものですね。クラスによって性能差がありますが、いずれも環境を認識して聴こえを最適化するので、約20年前と比べて、格段に実用的になりました。
AIの機能をフル活用したいなら両耳装用です。
これからはスマートフォンとの連動も必要ですね。
補聴器を買ってつけるだけではなく、脳が補聴器の音に慣れるように2~3ヶ月、リハビリが必要です。
リハビリ例
- 新聞・雑誌などを声に出して読む(音読する)
- ラジオを聴く
- 音読が習慣化されてきたら、できるだけ早く読む
- 文章追唱法(口型提示あり/口型提示なし)
聞き取りづらいからと補聴器を付けなくなるかたも多くいらっしゃいますが、リハビリをすることで、脳が音の聞き取りができるようようになるので、補聴器を購入された後は、ぜひリハビリをして音がより聞き取りやすくなるようトレーニングをしましょう。
購入から約2〜4年で、補聴器のマイク・レシーバー・充電池等が劣化してきます。近年の補聴器修理は、パソコンやスマートフォンと同じく内部部品一式を全交換することがほとんどです。要するに数年毎に有償修理することで、補聴器を新品同様にリフレッシュすることが可能ということです。※ただしメーカー修理受付期間内に限る
使用者が日頃出来ることは、耳栓部分のブラッシングと、機械乾燥と、汗や水で濡れたらこまめに、補聴器全体をメガネ拭きやティッシュ等で拭くことです。
常に3ヵ月分以上の電池を確保しておくことが重要です。
電池寿命は『カタログ等に掲載されている電池寿命(時間)×0.7※÷補聴器の平均使用時間/日』で計算できます。
※×0.7 は使用環境や使い方や自然放電による。
※平均使用時間/日は販売店スタッフに確認すれば教えてもらえます。
バッテリー付(蓄電機能付)の充電器を購入しておくと安心です。バッテリー無しの場合は、どのメーカーもおおよそ3〜4時間の充電で24時間使用出来る仕様です。節電の為に電源の切り方入れ方をスタッフに確認しておくと良いですね。
私自身、聴覚過敏、突発性難聴、メニエール病等急性難聴の既往歴があります。なので、難聴でつらい思いや心配をされているお客様(患者様)の気持ちがわかります。お気持ちに寄り添った仕事を心がけたいと思っております。